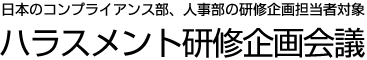第1回 なぜ、ハラスメント研修を受けても管理者は悩むのか?
職場のパワハラ問題の「実態」は見えていますか?
さて、一口に職場のパワハラ問題と言っても、その様相は単純ではありません。
私は企業内研修の講師として数多くの管理職対象ハラスメント研修を行ってきましたが、受講者である管理職の方々に「あなたの職場にはパワハラ問題はありませんか、あるとしたらそれはどのような事態ですか」と尋ねると、「パワハラ問題はあると思うが、あからさまなパワハラ行為があるというわけではなく、どのような事態かと聞かれてもよく分からない」という、なんとも曖昧な答えが返ってきます。
そして、
「どのような言動がパワハラになるのか分からない」
「何を言っても相手がパワハラだと思えばパワハラになるのだろうか」
という、なんとも心もとない思いを口にします。
これと似たような感覚を持たれる方も多いのではないでしょうか。
自分の職場のパワハラ問題について、なぜこのような曖昧で心もとない感覚になるのでしょうか。
それは、「管理職は真っ当な指導や注意をしているのに、それに対して部下が『パワハラだ』と反応する状況」のせいなのです。
(本文では、このような「状況」を「モヤハラ®状況」と名付けます。パワハラに似ているモヤモヤした状況という意味合いです。)
つまり、モヤハラ®状況があるにもかかわらずその存在を認識していないために、真っ当な指導がなぜパワハラと言われるのかが理解できず、「結局パワハラはいくら考えても埒があかない」という、
諦めにも似た心もとない感覚になるのです。
ハラスメント研修の受講者である管理職の方々からは、モヤハラ®状況を象徴するエピソードをたくさんお聞きしました。
その一例を紹介しましょう。
その電話が終わった後で
「営業は足で稼ぐものだ、資料は持参して世間話のひとつでもしてこい」と言ったら、部下から
「それってパワハラじゃないですか」と言われたそうです。
そしてその管理職は「私は指導のつもりだったのですが、私の言ったことはパワハラになるのでしょうかね。」と
首をひねっていました。
モヤハラ状況は放っておけない。
モヤハラ®状況が原因とする管理職の悩みを放置しておくと、いろいろな弊害が予想されます。
真っ当な指導をしたのに「パワハラだ」と言われたりすれば、管理職としてもいい気はしません。
「パワハラだ」という言葉を口にした部下としても、気分は穏やかではないでしょう。
そのようにして、管理職と部下との間に心の溝ができ、コミュニケーションが円滑に
とれなくなり、風通しの悪い職場になりかねません。
管理職として「正しい指導とパワハラの境界線はどこか」
という悩みが昂じると、「何を言っても相手がパワハラだと思えばパワハラになるのであれば、
面倒な指導や助言はなるべく避けよう」という考えになるかもしれません。
それはもはや、人材育成という管理職の重要な任務の放棄にほかなりません。
また、真っ当な指導に対しても心の中でパワハラだと感じている部下が居るのかもしれないという現実を認識しなければ、その管理職は同じ言動を繰り返し、その結果、その部下はプレッシャーを受け続けることになり、メンタルヘルスのバランスを崩すという深刻な事態にもなりかねません。
そのような弊害を避けるためには、管理職を対象として、その悩みを解消するような研修が必要になります。
受講生に効果のない研修の事例
市販のハラスメントDVD教材を使用して研修をする会社が増えています。
問題はその内容。
暴力や労働法違反で裁判になったケースや、社内外の相談窓口に寄せられた
相談内容を使ってパワハラ問題を説明しても、受講者(管理職)にしてみれば
「それは境界線を越えた真っ黒なケースであり、パワハラと言われても当然だろう」
と受け取るだけで、現場において悩ましいと感じられているパワハラの問題が
解消されることはありません。
(そのような深刻かつ極端なケースについての解説は、人事部の担当者に対しては有効であり、意味を持つ)
また、「暴力行為や労働法違反行為、あるいは人間としてあるまじき暴言などは
パワハラになるので注意しましょう」と言われても、
何をどうすればよいかが示されていないし、多くの受講者(管理職)は常識的な人間
であり、暴力行為や労働法違反行為、あるいは人間としてあるまじき暴言などとは 無縁です。
ハラスメントを理解するにあたり、一番の論点は上述のポイントではないのです。
また、厚労省の定義だけを理解しても、本当に職場の管理職が感じている
「モヤモヤとした疑問」の解決には不十分なのです。

アーサーアンダーセン、アンダーセンコンサルティング、リシュモンジャパン株式会社等の外資系企業の総務・法務部で契約書作成・レビューを中心とする企業法務業務に従事。その後、KPMGあずさビジネススクール株式会社で研修講師を務め、株式会社インプレッション・ラーニングにおいてコンプライアンス、企業法務を中心とする講師を務める。著書「やさしくわかるコンプライアンス~茶髪は違反ですか?」(日本実業出版社)「現場で役立つ!ハンコ・契約書・印紙のトリセツ」(日本経済新聞出版社)